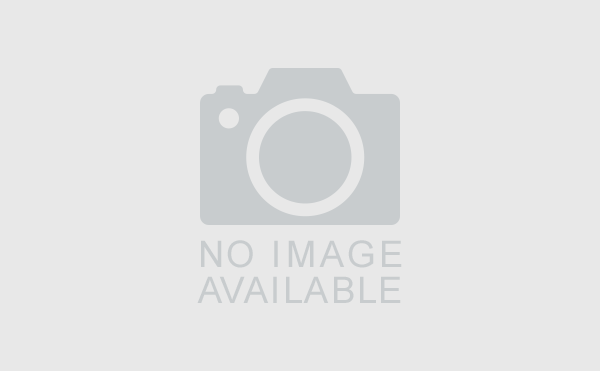【介護DX】排泄センサーが難しい理由とは?
フィジカルプログラミングとロボットの例
「フィジカルプログラミング」とは、ロボットやセンサー、LEDといった物理的な機器をプログラムで制御し、実際に動かしながら改良していく手法です。
たとえばロボットなら、動かしてみることで「速い/遅い」「大きい/小さい」「角度/長さ」などの違いを目で確認でき、その結果をもとにプログラムを改善することができます。
おむつモニター(排泄センサー)の難しさ
一方で、介護現場で使われる「排泄センサー(おむつモニター)」は異なります。プログラマーは実際におむつの中を見ることができないため、「今排便があった」「排尿があった」といった事実を直接確認できません。
そのため、社内でニオイや湿度を人工的に変化させてテストしても、実際の介護施設ではうまく機能しない場合があります。
介護現場の複雑な条件
高齢者介護の現場では、
- 利用者ごとの体質や健康状態
- センサーごとの個体差
- 気候や湿度などの環境要因
- 生活リズムの違い
といった多様な条件が重なり合います。
そのため「万能なプログラム」を開発することは難しく、現場の声を取り入れた継続的な改良が欠かせません。
データ見える化と介護DXの重要性
そこで必要なのが「排泄センサーのデータ見える化」です。
データを介護担当者と共有し、現場からのフィードバックを得ることで、より正確で信頼できるおむつモニターへと進化させることができます。これは単なるセンサー開発ではなく、介護DX(デジタルトランスフォーメーション)を実現する重要なステップです。
まとめ
ロボットのように「動作が見える」対象なら、プログラムの改良は比較的容易です。しかし、排泄センサーのように「見えない現象」を扱う場合は格段に難易度が高くなります。
だからこそ、データの見える化 × 介護現場との連携 が成功の鍵になります。排泄センサーは介護の負担軽減や高齢者の生活の質向上につながる技術であり、今後ますます注目される分野です。
👉 詳しくは、弊社 株式会社エフエージェイ(FAJ)公式サイト をご覧ください。
製品情報は 排泄センサー・おむつモニターのページ でご紹介しています。